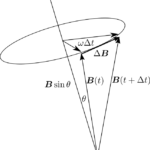$\def\bm#1{{\boldsymbol{#1}}}
\def\coloneqq{{:=}}
\newcommand{\rmd}{\mathrm{d}}$
第11講の導入
今回は外力として周期的外力が加わる場合の振動、強制振動について学ぶことにしましょう。計算が複雑になってきていますので、これまでに扱った常微分方程式の解説と振動の解説のところを復習しながら読み進めていってください。
減衰を伴わない強制振動
振り子の上端を水平に振動させて、振動方向に外力を加えた場合の運動を強制振動と言います。ここでは、振動数$\omega$の正弦波で書ける周期的外力を考えてみましょう。このとき、運動方程式は
\[
m \frac { d ^ { 2 } x } { d t ^ { 2 } } = – k x + F _ { 0 } \sin \omega t
\]
となります。強制振動外力$F_0\sin{\omega t}$がある線型微分方程式は非斉次方程式または非同次方程式と呼ばれています。ここでは、まずその特殊解について考えてみましょう。先ほどの運動方程式の両辺を$m$で割ると、
\[
\ddot { x } + \omega _ { 0 } ^ { 2 } x = f _ { 0 } \sin \omega t
\]
となります。ここで、$\omega_0^2=k/m$、$f_0=F_0/m$です。解の形を$x(t)=a\sin{\omega t}$と仮定して直前の式に代入してみると、
\[
a = \frac { f _ { 0 } } { \omega _ { 0 } ^ { 2 } – \omega ^ { 2 } }
\]
となります。外力の振動数が元の振動数より大きい場合、すなわち$\omega>\omega_0$の場合、$a$は負になります。これは外力と逆向きに振動することをあらわしています。振幅$|a|$は$\omega$が$\omega_0$に近づくと増大し、$\omega=\omega_0$のとき発散します。強制力の振動数を固有振動数に近づけたことによって、振幅の大きな振動が誘起される現象のことを共振現象あるいは共鳴現象と言います。
強制振動外力$F_0\sin{\omega t}$を除いた斉次方程式の解は、今の場合調和振動子の解の形
\[
x ( t ) = A \cos \omega _ { 0 } t + B \sin \omega _ { 0 } t
\]
で与えられます。非斉次方程式の一般解は、次の式のように、非斉次方程式の特殊解に斉次方程式の一般解を加えたもので与えられます。
\[
x ( t ) = A \cos \omega _ { 0 } t + B \sin \omega _ { 0 } t + \frac { f _ { 0 } } { \omega _ { 0 } ^ { 2 } – \omega ^ { 2 } } \sin \omega t
\]
一般解が求まったので、初期条件による解の構成を考えていきましょう。$t=0$まで静止していた質点に$t=0$から共進振動数で$f_0\sin{\omega t}$の強制振動外力をかけるときの質点の振る舞いを議論しましょう。一般の振動数$\omega$での一般解において初期条件、
\[
\begin{array} { l } { x ( 0 ) = A = 0 } \\ { \dot { x } ( 0 ) = B \omega _ { 0 } + \dfrac { f _ { 0 } \omega } { \omega _ { 0 } ^ { 2 } – \omega ^ { 2 } } = 0 } \end{array}
\]
を満たすようにすると、
\[
B = – \frac { \omega } { \omega _ { 0 } } \frac { f _ { 0 } } { \omega _ { 0 } ^ { 2 } – \omega ^ { 2 } }
\]
となり、これに解を代入すると
\[
x ( t ) = \frac { f _ { 0 } } { \omega _ { 0 } ^ { 2 } – \omega ^ { 2 } } \left( \sin \omega t – \frac { \omega } { \omega _ { 0 } } \sin \omega _ { 0 } t \right)
\]
となります。強制外力の振動数を$\omega=\omega_0+\varepsilon$として、$\varepsilon\rightarrow0$の極限を取ることで固有振動数に近づけることを考えてみます。このとき、
\[
x ( t ) = \frac { – f _ { 0 } } { \left( 2 \omega _ { 0 } + \varepsilon \right) \varepsilon } \left( \sin \omega _ { 0 } t \cos \varepsilon t + \cos \omega _ { 0 } t \sin \varepsilon t – \frac { \omega _ { 0 } + \varepsilon } { \omega _ { 0 } } \sin \omega _ { 0 } t \right)
\]
となります。分母・分子共に$\varepsilon$について$1$次の項のみを残すことにして
\[
\begin{array} { l } { \cos \varepsilon t \approx 1 – \dfrac { ( \varepsilon t ) ^ { 2 } } { 2 } \approx 1 } \\ { \text { sin } \varepsilon t \approx \varepsilon t } \end{array}
\]
を用いると、
\[
\begin{aligned} x ( t ) & = \lim _ { \varepsilon \rightarrow 0 } \frac { – f _ { 0 } } { 2 \omega _ { 0 } \varepsilon } \left( \varepsilon t \cos \omega _ { 0 } t – \frac { \varepsilon } { \omega _ { 0 } } \sin \omega _ { 0 } t \right) \\ & = – \frac { f _ { 0 } } { 2 \omega _ { 0 } } \left( t \cos \omega _ { 0 } t – \frac { \sin \omega _ { 0 } t } { \omega _ { 0 } } \right) \end{aligned}
\]
となります。第$1$項は強制振動により振幅が時間に比例して増大していくことをあらわしているとみることが出来ます。
減衰を伴う強制振動
次は抵抗力$-2\gamma\dot{x}$がはたらく場合を考えてみましょう。解の形として、
\[
x=A\cos{\omega t}+B\sin{\omega t}
\]
を仮定して$\cos{\omega t}$と$\sin{\omega t}$それぞれで方程式を立てると、
\[
A=\frac{-2\gamma\omega f_0}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2} , B=\frac{(\omega_0^2-\omega^2)f_0}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2}
\]
と求めることが出来ます。$x=a\sin{(\omega t-\delta)}$とおくと、
\[
a=\frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2}} , \tan{\delta}=\frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2-\omega^2}
\]
と結ぶことが出来ます。減衰項があるため、振幅が発散することはありませんが$\omega=\omega_0$付近で大きく増大します。
振幅を最大化する振動数を共進振動数$\omega_{\mathrm{res}}$と呼ぶことにしましょう。これが最小になるのは、
\[
\left( \omega _ { 0 } ^ { 2 } – \omega ^ { 2 } \right) ^ { 2 } + 4 \gamma ^ { 2 } \omega ^ { 2 }
\]
が最小になる振動数であり、
\[
\omega _ { \mathrm { res } } = \sqrt { \omega _ { 0 } ^ { 2 } – 2 \gamma ^ { 2 } }
\]
となる。減衰のないとき($\gamma=0$)は$\omega=\omega_0$ですが、$\gamma$が大きくなって少しずつ共進振動数が小さくなっていくと共に、振幅のピークは低くなり、幅は広がることになります。$\gamma>\omega_0/\sqrt{2}$になると、振幅が最大になるのは$\omega=0$のときになって、共振現象は見られなくなります。
第11講のまとめ
最後に一言コメントをして第講を終わりにしましょう。今回扱った強制振動・共振現象は日常でも見られることがあります。
2011年3月11日に起こった東北地方太平洋沖地震において、震源から数100[km]離れた大阪は比較的揺れが小さく震度3程度だったにもかかわらず、地上55階の大阪府庁咲洲庁舎では3[m]もの横揺れが10分程度続いて、天井や壁に300カ所以上の被害が出ました。 これはこの建物の地盤が弱く、地盤の揺れの周期が6.5[s]と長くなり、高いビルと共振現象を起こしたためと考えられています。これは高校物理でやった気柱や弦の振動と同様に、ビルが高くなれば共鳴振動数は低くなります。従って、ガタガタ揺れる周期1[s]程度の地震では低層の住宅の被害が大きく、周期が長い地震になると高層のビルが大きく揺れるようになるということが知られています。