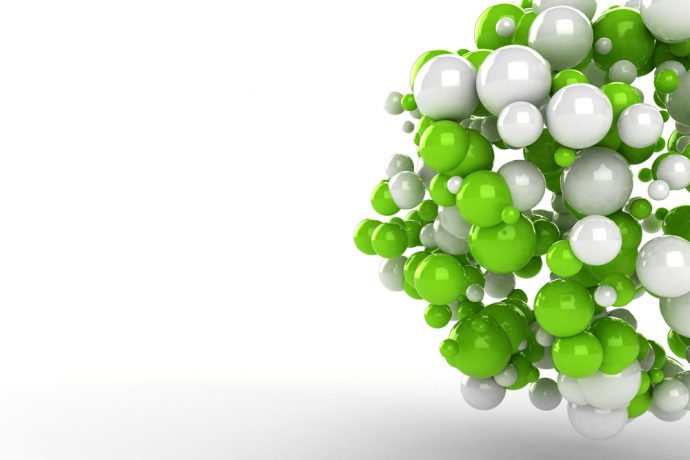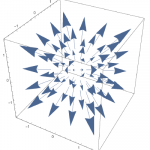$\def\bm#1{{\boldsymbol{#1}}}
\def\coloneqq{{:=}}
\newcommand{\car}{\mathcal{R}}
\newcommand{\bcar}{\bm{\mathcal{R}}}
\newcommand{\hcar}{\bm{\hat{\mathcal{R}}}}
\newcommand{\hbx}{\bm{\hat{x}}}
\newcommand{\hby}{\bm{\hat{y}}}
\newcommand{\hbz}{\bm{\hat{z}}}
\newcommand{\hbr}{\bm{\hat{r}}}
\newcommand{\hbtheta}{\bm{\hat{\theta}}}
\newcommand{\hbphi}{\bm{\hat{\phi}}}
\newcommand{\hbs}{\bm{\hat{s}}}
\newcommand{\bmsa}{\bm{a}}
\newcommand{\bmsb}{\bm{b}}
\newcommand{\bmsc}{\bm{c}}
\newcommand{\bmsd}{\bm{d}}
\newcommand{\bmse}{\bm{e}}
\newcommand{\bmsf}{\bm{f}}
\newcommand{\bmsg}{\bm{g}}
\newcommand{\bmsh}{\bm{h}}
\newcommand{\bmsi}{\bm{i}}
\newcommand{\bmsj}{\bm{j}}
\newcommand{\bmsk}{\bm{k}}
\newcommand{\bmsl}{\bm{l}}
\newcommand{\bmsm}{\bm{m}}
\newcommand{\bmsn}{\bm{n}}
\newcommand{\bmso}{\bm{o}}
\newcommand{\bmsp}{\bm{p}}
\newcommand{\bmsq}{\bm{q}}
\newcommand{\bmsr}{\bm{r}}
\newcommand{\bmss}{\bm{s}}
\newcommand{\bmst}{\bm{t}}
\newcommand{\bmsu}{\bm{u}}
\newcommand{\bmsv}{\bm{v}}
\newcommand{\bmsw}{\bm{w}}
\newcommand{\bmsx}{\bm{x}}
\newcommand{\bmsy}{\bm{y}}
\newcommand{\bmsz}{\bm{z}}
\newcommand{\bma}{\bm{A}}
\newcommand{\bmb}{\bm{B}}
\newcommand{\bmc}{\bm{C}}
\newcommand{\bmd}{\bm{D}}
\newcommand{\bme}{\bm{E}}
\newcommand{\bmf}{\bm{F}}
\newcommand{\bmg}{\bm{G}}
\newcommand{\bmh}{\bm{H}}
\newcommand{\bmi}{\bm{I}}
\newcommand{\bmj}{\bm{J}}
\newcommand{\bmk}{\bm{K}}
\newcommand{\bml}{\bm{L}}
\newcommand{\bmm}{\bm{M}}
\newcommand{\bmn}{\bm{N}}
\newcommand{\bmo}{\bm{O}}
\newcommand{\bmp}{\bm{P}}
\newcommand{\bmq}{\bm{Q}}
\newcommand{\bmr}{\bm{R}}
\newcommand{\bms}{\bm{S}}
\newcommand{\bmt}{\bm{T}}
\newcommand{\bmu}{\bm{U}}
\newcommand{\bmv}{\bm{V}}
\newcommand{\bmw}{\bm{W}}
\newcommand{\bmx}{\bm{X}}
\newcommand{\bmy}{\bm{Y}}
\newcommand{\bmz}{\bm{Z}}
\newcommand{\rmd}{\mathrm{d}}$
第4回目は荷電粒子からの輻射について扱いました。
第5回目となる今回は、量子力学における行列計算に馴染むためにDirac 方程式の問題を扱います。
問題
[問題1]電磁場中のDirac 方程式は電荷を$e$として
\[
i\hbar\dfrac{\partial\psi}{\partial t}=\left\{c\left[\sum_j\left(p_j-\dfrac{e}{c}A_j\right)\hat{\alpha}_j+mc\hat{\beta}\right]+e\phi~\hat{1}\right\}
\]
と与えられる。静磁場に対して$\psi\propto\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$、$\phi=0$としたとき、$\psi$を$2$成分の$\chi_1$、$\chi_2$を用いて
\[
\psi=\left(
\begin{array}{l}
\chi_1\\
\chi_2
\end{array}
\right)
\]
とあらわすと
\[
\left\{
\begin{array}{rcl}
(E-mc^2)\chi_1&=&c\displaystyle\sum_j\left(p_j-\dfrac{e}{c}A_j\right)\sigma_j\chi_2\\
&&\\
(E+mc^2)\chi_2&=&c\displaystyle\sum_j\left(p_j-\dfrac{e}{c}A_j\right)\sigma_j\chi_1
\end{array}
\right.
\]
を得る。ここで、$E=\varepsilon+mc^2$、$|\varepsilon|\ll mc^2$とおくと、
\[
\varepsilon\chi_1=\displaystyle\left[\frac{1}{2m}\sum_j\left(p_j-\frac{e}{c}A_j\right)^2-\frac{e\hbar}{2mc}\sum_j(\nabla\times \bm{A})_j\sigma_j\right]\chi_1
\]
が成り立ち、スピン$\sigma_j$が磁気モーメントとして外部磁場と相互作用することを示せ。
[問題2]中心力場のHamiltonian
\[
\hat{H}=\sum_j\dfrac{c\hbar}{i}\dfrac{\partial}{\partial x_j}\hat{\alpha}_j+mc^2\hat{\beta}+v(r)\hat{1}
\]
に対して、$\hat{H}$と$\hat{\bm{j}}$が交換可能であることを示せ。
[問題3]中心力場のDirac 方程式の動径成分
\[
\left\{
\begin{array}{rcl}
F’&=&-\dfrac{\kappa}{r}F+\left[\dfrac{2}{\alpha}+\alpha(\varepsilon-v)\right]G\\
&&\\
G’&=&+\dfrac{\kappa}{r}G-\alpha(\varepsilon-v)F
\end{array}
\right.
\]
より、次の式が成り立つことを示せ。
\begin{align}
F”=&\dfrac{\kappa(\kappa+1)}{r^2}F-2(\varepsilon-v)F\nonumber\\
&-\alpha^2(\varepsilon-v)^2F-\dfrac{\alpha^2}{2}v’F’-\dfrac{\alpha^2}{2}\dfrac{\kappa}{r}v’F+O(\alpha^4)\nonumber
\end{align}
但し、右辺第2項まで(1行目)がSchodinger 方程式の動径線分に対応していて、第3項以降(2行目)が最低次の相対論補正に対応している。
[問題4]問題3の右辺第5項は
\[
-\displaystyle\frac{\alpha^2}{2}\frac{\kappa}{r}v’=\frac{\alpha^2}{2r}v’+\frac{\alpha^2}{r}v'(\bm{l}\cdot\bm{s})
\]
とあらわせることを示せ。但し、
\[
2\bm{l}\cdot\bm{s}=(\bm{l}+\bm{s})^2-\bm{l}^2-\bm{s}^2
\]
であり、$(\bm{l}\cdot\bm{s})$の項をスピン軌道相互作用と呼ぶ。
演習問題解答
[問題1]
問題には以下の連立方程式が与えられている。
\begin{align}
(E-mc^2)\chi_1=&c\sum_j\left(p_j-\displaystyle\frac{e}{c}A_j\right)\sigma_j\chi_2\\
(E+mc^2)\chi_2=&c\sum_j\left(p_j-\displaystyle\frac{e}{c}A_j\right)\sigma_j\chi_1
\end{align}
式(1)・(2)を与えられた条件に従って書き換えればそれぞれ
\begin{align}
\varepsilon\chi_1=&\sum_j\left(cp_j-eA_j\right)\sigma_j\chi_2\\
\chi_2=&\frac{1}{E+mc^2}\sum_j\left(cp_j-eA_j\right)\sigma_j\chi_1
\end{align}
となる。式(3)へ式(4)を代入して$\chi_2$を消去すれば
\begin{align}
\varepsilon\chi_1=&\displaystyle\sum_j\left(cp_j-eA_j\right)\sigma_j\chi_2=\displaystyle\frac{1}{\varepsilon+2mc^2}\sum_i\sum_j\left(cp_i-eA_i\right)\left(cp_j-eA_j\right)\sigma_i\sigma_j\chi_1\nonumber\\
=&\displaystyle\frac{1}{\varepsilon+2mc^2}\sum_j\left(cp_j-eA_j\right)^2\sigma_j^2\chi_1+\displaystyle\frac{1}{\varepsilon+2mc^2}\sum_{i\neq j}\left(cp_i-eA_i\right)\left(cp_j-eA_j\right)\sigma_i\sigma_j\chi_1\nonumber\\
\simeq&\displaystyle\frac{1}{2mc^2}\sum_j\left(cp_j-eA_j\right)^2\sigma_j^2\chi_1+\displaystyle\frac{i^2e\hbar c}{2mc^2}\sum_{k}(\nabla\times\bm{A})_k\sigma_k\chi_1\nonumber\\
=&\displaystyle\left[\frac{1}{2m}\sum_j\left(p_j-\frac{e}{c}A_j\right)^2-\frac{e\hbar}{2mc}\sum_j(\nabla\times \bm{A})_j\sigma_j\right]\chi_1\nonumber
\end{align}
となり所望の式を得る。因みに、付加的なエネルギー項のHamiltonian $\hat{H}_{\mathrm{Dipole}}$は
$\hat{H}_{\mathrm{Dipole}}=-\displaystyle\frac{e\hbar}{2mc}\sum_j(\nabla\times \bm{A})_j\sigma_j=-\displaystyle\frac{e\hbar}{2mc}\bm{\sigma}\cdot\bm{B}$と書ける。
これは磁場$\bm{B}$の中で磁気双極子モーメント$\displaystyle\frac{e\hbar}{2mc}\bm{\sigma}$が得るエネルギーと解釈できる。
すなわち、非相対論極限ではDirac 方程式から、電子は磁場中に置かれると磁気双極子モーメント$\displaystyle\frac{e\hbar}{2mc}\bm{\sigma}$を持つように振る舞うと言うことが出来る。
[問題2]
$\bm{\Sigma}\coloneqq\left(
\begin{array}{cc}
\bm{\sigma}&0\\
0&\bm{\sigma}
\end{array}
\right)$と定義すれば$[\bm{S},\hat{H}]$において可換でない要素は行列の部分のみとなる。
具体的な表示を$[\sigma_i,\sigma_j]=2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$を用いて計算すれば、$[\Sigma_i,\alpha_j]=2i\varepsilon_{ijk}\alpha_k$及び\\$[\Sigma_i,\beta]=0$が成り立つ。これより$[S_i,\hat{H}]=i\hbar c\varepsilon_{ijk}\alpha_kp_j=-i\hbar c(\bm{\alpha}\times\bm{p})_i$となる。この結果は、相互作用のない自由粒子を扱っているのにも関わらずスピンがHamiltonian と同時対角化不可能、つまり運動の定数ではないことを示している(但し、$\bm{p}=\bm{0}$のときだけ例外的に$[\bm{S},\hat{H}]=0$となる。)。
次に$[L_i,\hat{H}]$を求める。これは正準交換関係$[x_i,p_j]=i\hbar\delta_{ij}$を用いて、$[L_i,\hat{H}]=i\hbar c(\bm{\alpha}\times\bm{p})_i$つまりこれも運動の定数ではない。
よって$\bm{J}$は確かに$[J_i,\hat{H}]=0$を満たす。これは運動の定数である。これらの結論はDirac 方程式において角運動量とスピンが不可分の要素であることを示している。
[問題3]
問題には以下の連立方程式が与えられている。
\begin{align}
F’=&-\displaystyle\frac{\kappa}{r}F\left[\frac{2}{\alpha}+\alpha(\varepsilon-v)\right]G\\
G’=&\displaystyle\frac{\kappa}{r}G-\alpha(\varepsilon-v)F
\end{align}
これを$r$で微分して
\[
F”=\displaystyle\frac{\kappa}{r^2}F-\frac{\kappa}{r}F’+\left[\frac{2}{\alpha}+\alpha(\varepsilon-v)\right]G’-\alpha v’G
\]
$G$、$G’$を消去するためにこれらをそれぞれ用いて
\begin{align}
F”=&\displaystyle\frac{\kappa(\kappa+1)}{r^2}F-2(\varepsilon-v)F-\alpha^2(\varepsilon-v)^2F-\left(F’+\frac{\kappa}{r}F\right)\frac{\alpha^2v’}{2+\alpha^2(\varepsilon-v)}\nonumber\\
\simeq&\displaystyle\frac{\kappa(\kappa+1)}{r^2}F-2(\varepsilon-v)F-\alpha^2(\varepsilon-v)^2F-\frac{\alpha^2}{2}v’F-\frac{\alpha^2}{2}\frac{\kappa}{r}v’F+\mathcal{O}(\alpha^4)
\end{align}
よって題意は示された。但し、式(8)において$\mathcal{O}(\alpha^4)=\left(F’+\displaystyle\frac{\kappa}{r}F\right)\displaystyle\frac{(\varepsilon-v)\alpha^4v’}{4}$である。
さて、簡単に分かることとして、$r\rightarrow\infty$の極限でこれらは調和振動子の式になる。すなわち、無限大の極限では相互作用が”解ける”と形容して良いだろう。なお、この事実から関数形を予想し冪級数解法的に解くことでこれらの式を求積することが出来るが、本問から逸れるため省略する。
[問題4]
$-(1+\kappa)F=2(\bm{l}\cdot\bm{s})F$が示せればいい。与えられた条件を利用すれば、
\begin{align}
&2(\bm{l}\cdot\bm{s})F=(\bm{j}^2-\bm{l}^2-\bm{s}^2)F=\left\{j(j+1)-l(l+1)-\displaystyle\frac{3}{4}\right\}F\nonumber\\
=&\left\{
\begin{array}{l}
\left\{j(j+1)-\left(j+\displaystyle\frac{1}{2}\right)\left(j+\displaystyle\frac{3}{2}\right)-\displaystyle\frac{3}{4}\right\}F \left(\mathrm{for}~l=j+\displaystyle\frac{1}{2}\right)\\
\left\{j(j+1)-\left(j-\displaystyle\frac{1}{2}\right)\left(j+\displaystyle\frac{1}{2}\right)-\displaystyle\frac{3}{4}\right\}F \left(\mathrm{for}~l=j-\displaystyle\frac{1}{2}\right)
\end{array}
\right.\nonumber\\
=&\left\{\begin{array}{r}
\left(-j-\displaystyle\frac{3}{2}\right)F \left(\mathrm{for}~l=j+\displaystyle\frac{1}{2}\right)\\
\left(j-\displaystyle\frac{1}{2}\right)F \left(\mathrm{for}~l=j-\displaystyle\frac{1}{2}\right)
\end{array}
\right.=-(1+\kappa)F\nonumber
\end{align}
よって題意は示された。因みに、これらの式から明らかに$\kappa(\kappa+1)=l(l+1)$が両方の場合に成り立つ。これは連立微分方程式が動径方程式の形で書けることを保証している。
参考文献
[1]川村嘉春、『相対論的量子力学』、裳華房、2013