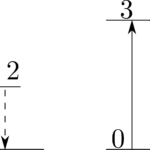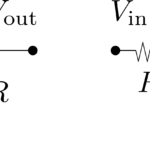$\def\bm#1{{\boldsymbol{#1}}}$
$\def\rmd#1{\mathrm{d}{#1}}$
$\def\Braket#1{\langle{#1}\rangle}$
$\def\Bra#1{\langle{#1}|}$
$\def\Ket#1{|{#1}\rangle}$
$\def\kb{k_{\text{B}}}$
$\def\dag{\dagger}$
物理学実験4
光子相互作用

光子は電荷を持たないので荷電粒子と同じ種類の相互作用はしないが、電磁気力を取り次ぐため他の荷電粒子と様々な相互作用をする。特に以下の$3$種類が頻出である。
光吸収
光子が原子に完全に吸収されると、代わりに$E_\gamma-E_b$のエネルギーを持った電子が放出される。ここで、$E_\gamma$は入射した光子のエネルギーで$E_b$は電子の結合エネルギーである。これは低エネルギー(数keV)の光子において支配的なプロセスである。
光子が孤立した原子ではなくバルク物質に吸収される場合は、仕事関数$\phi$という形に集約された余分な表面効果があらわれる。放出された電子の最大エネルギーは$E_{\text{max}}=E_\gamma-\phi$で与えられる。様々な材料の仕事関数に関係する問題が頻繁に出題されるため、これらの用語と表記法は覚えておく価値がある。
コンプトン散乱
光子が原子の電子に対して弾性的に散乱すると、電子は原子から追い出される。光子の散乱角が広ければ広いほど、電子は多くのエネルギーを失う。これは中間的なエネルギー(数$10$~keV から数MeV)の光子において支配的なプロセスである。この現象においては粒子の質量$m$を用いてあらわすことができるコンプトン波長$\lambda$が重要な役割を果たす。ド・ブロイ波長と異なり、コンプトン波長は粒子の運動量には依存せず、質量のみに依存する。コンプトン散乱による光の波長のずれ$\Delta\lambda$は以下の公式であらわされる。
\begin{equation}
\lambda=\dfrac{h}{mc}~,~\Delta\lambda=\dfrac{h}{mc}(1-\cos{\theta})
\end{equation}
エネルギーのずれを問われる場合もあるが、その場合はこの公式とアインシュタインの関係式$E=hf=hc/\lambda$を併用すれば良い。
対生成
$E_\gamma>2m_ec^2$のとき、核の周りの電場は光子を誘導し電子・陽子対を生成する。これは高エネルギー(数$10$~MeV 以上)の光子において支配的なプロセスである。電子の質量が大体$0.5~\text{MeV}$なので、対生成の閾値は$1~\text{MeV}$程度である。
光吸収は原子全体との相互作用、コンプトン散乱は原子の電子との相互作用、対生成は原子核との相互作用であるということに注意しなければならない。これら$3$つのプロセスの確率は吸収側の原子番号$Z$に比例する。$Z$は原子の電子がどれくらい存在しているかという値にもなっているためである。より詳細には、対生成の確率は$Z^2$、コンプトン散乱の確率は$Z$、光吸収の確率は$Z^4$に大体比例している。タングステンのように$Z$の大きい物質を利用する目的は、これらの相互作用が起こる確率、特に低エネルギーでより支配的である光吸収が起こる確率を高めるためである。
粒子検出器の諸性質
粒子検出器とはその名の通り、やって来る粒子を検出するための装置である。やってきた粒子のエネルギーを測る装置をカロリメータ―と呼ぶ。エネルギーを測るためには、物質中でのエネルギー損失を利用したり、エネルギーを吸収するもの(原子の電子、光電子、生成された電子・陽子対など)を用いたりする。荷電粒子の場合は検出が容易であるが、それ以外の粒子の場合はどうにかして信号を増幅させる必要がある。
信号の増幅を必要とする最も典型的な例は光子である。光子$1$個につき電子が$1$個しか放出されないため、検出は困難である。このような事情から、光子の検出はしばしば題材にされる。光子の相互作用断面積を増やすためには$Z$の大きな物質が必要であるが、これにはNaI/Tl と呼ばれる、微量のタリウム(Tl)を含むヨウ化ナトリウム(NaI)の結晶からなるシンチレーターが良く用いられる($Z=53$)。シンチレーターとは通過する荷電粒子によって強度が電子のエネルギーに比例するような可視光を生成するような装置のことをいう。これらの可視光子は光電子増倍管と呼ばれる光電効果のカスケードを利用してマクロな電流を作る装置に繋がれる。最終的にはいくつかの分析器に掛けられて、電流は生の電圧に変換される。理想的には、光子のエネルギーは出力電圧に比例し、検出器は既知のエネルギーの光子源を照射することで較正できる。
放射性崩壊
物質が放射性崩壊を起こすとき、ある時刻$t$での放射性物質の原子の個数$N(t)$は$t=0$での粒子数$N_0$を用いて次のような式に従う。
\begin{equation}
N(t)=N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}
\end{equation}
ここで、$1/\lambda$は粒子の平均寿命をあらわす。特に、粒子の半減期$t_{1/2}$は$(\ln{2})/\lambda$である。