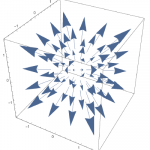$\def\bm#1{{\boldsymbol{#1}}}$
$\def\rmd#1{\mathrm{d}{#1}}$
$\def\Braket#1{\langle{#1}\rangle}$
$\def\Bra#1{\langle{#1}|}$
$\def\Ket#1{|{#1}\rangle}$
$\def\kb{k_{\text{B}}}$
$\def\dag{\dagger}$
量子力学09
今回は近似法の問題を考えていきます。
近似法には大きく分けて、摂動論、変分法、断熱定理の$3$テーマが存在する。摂動論の計算が最もよく出題される。変分法を実際に適用する問題は計算量が多いためあまり出題されない。断熱定理は発見的に利用する類の問題がしばしば出題される。
時間に依存しない摂動論
量子系のHamiltonian が$H=H_0+\lambda H’$で書けるとする。ここで、$\lambda$は無次元の数で$1$よりも十分小さいとする。また、$H_0$の固有エネルギー$E_n^0$とそれに対応する固有関数$\psi_n^0$が正確に分かっていて、$H’$は時間に依存しないとする。このとき、$n$番目の準位の$1$次のずれは以下のように書ける。
\begin{equation}
E_n=E_n^0+\lambda\Braket{\psi_n^0|H’|\psi_n^0}
\end{equation}
$1$次のずれの計算は改めてSchr\”{o}dinger 方程式を解く必要がないので簡単である。もし$1$次のずれが対称性から$0$になる場合、$2$次のずれを考えることになる。$2$次のずれは以下のように計算することができる。
\begin{equation}
E_n=E_n^0+\lambda^2\sum_{m\neq n}\dfrac{|\Braket{\psi_m^0|H’|\psi_n^0}|^2}{E_n^0-E_m^0}
\end{equation}
$2$次のずれについては式を丸々覚えるよりも、ずれが$\lambda^2$で効いていること、第$2$項の分子は非負になるのでずれの符号は分母によること、縮退がある場合は上の式が定義できないことを理解しておけばよい。\\
摂動を考えるときは、計算する前にまず対称性の利用を考えること。例えば、ポテンシャルが$V(x)=m\omega^2x^2/2$の調和振動子が電場$\bm{E}=E_0\hat{\bm{x}}$の中にいるとき、摂動は$V(x)=-qEx$であるが、調和振動子の基底状態の波動関数は偶関数なので摂動は$1$次の寄与を持たず、$E_0^2$のオーダーで初めて非ゼロの寄与が現れることになる。Coulomb 型ポテンシャル$V(r)\sim r^{-1}$の中の水素原子についても同様である。
断熱定理
粒子がHamiltonian $H$であらわされる$n$番目の固有状態を取るとする。断熱定理は、このHamiltonian $H$がゆっくりと$H’$に変化した場合に粒子がHamiltonian $H’$に対応するという主張である。故に、断熱定理が成り立つとき、最終的なエネルギーは新たなパラメーターを用いて書ける新たなHamiltonian $H’$に対応したものになる。典型的な問題は、$1$次元の無限に深い井戸型ポテンシャルや調和振動子でポテンシャルの広さやバネ定数など、何らかのパラメーターが変化するというものである。