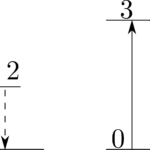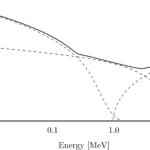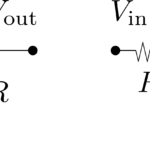$\def\bm#1{{\boldsymbol{#1}}}$
$\def\rmd#1{\mathrm{d}{#1}}$
$\def\Braket#1{\langle{#1}\rangle}$
$\def\Bra#1{\langle{#1}|}$
$\def\Ket#1{|{#1}\rangle}$
$\def\kb{k_{\text{B}}}$
$\def\dag{\dagger}$
物理学実験1
ここでは誤差解析の基本をまとめていきます。
標本分散
測定誤差は標準偏差によってあらわされる:
\begin{equation}
\sigma^2_{\text{S}}=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2
\end{equation}
例えば、質量の測定が$m=5\pm2~\text{kg}$なら、平均$\bar{x}$は$5~\text{kg}$で標準偏差$\sigma$は$2~\text{kg}$である。故に、標本分散は$\sigma^2=4~\text{kg}^2$である。
非常にたくさんの測定を行うと、測定結果は平均$\bar{x}$、標準偏差$\sigma$のガウス分布に近づいていく。このとき、この分布から無作為に標本$x$を取ると、$\bar{x}\pm\sigma$の範囲に$x$が存在している確率は$68\%$、$\bar{x}\pm2\sigma$の範囲に$x$が存在している確率は$95\%$である。
誤差の伝播
統計誤差$\sigma_{\text{stat}}$と系統誤差$\sigma_{\text{sys}}$を用いると、合計の誤差は$\sigma_{\text{tot}}=\sqrt{\sigma_{\text{stat}}^2+\sigma_{\text{sys}}^2}$となる。
相関のない$2$つの測定値$A\pm\sigma_A$、$B\pm\sigma_B$と不確かさのない定数$a$を用いて、$f(A,B)$の標準偏差$\sigma_f$は以下の公式で計算できる。
\begin{equation}
\sigma_f=\sqrt{\left(\dfrac{\partial f}{\partial A}\right)^2\sigma_A^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial B}\right)^2\sigma_B^2}
\end{equation}
これにより、標準偏差の式は以下のようにまとめられる。
\begin{equation}
\left\{
\begin{array}{lllll}
f=aA,&\sigma_f=a\sigma_A,&&f=A\pm B,&\sigma_f=\sqrt{\sigma_a^2+\sigma_B^2},\\
&&&&\\
f=AB,&\sigma_f=f\sqrt{\left(\dfrac{\sigma_A}{A}\right)^2+\left(\dfrac{\sigma_B}{B}\right)^2},&&f=\dfrac{A}{B},&\sigma_f=f\sqrt{\left(\dfrac{\sigma_A}{A}\right)^2+\left(\dfrac{\sigma_B}{B}\right)^2}
\end{array}
\right.
\end{equation}
重み付き平均
$1$つの量が$2$つの方法で測定され、$a+\sigma_x$、$y+\sigma_y$が得られたとする。これらの値から重み付き平均$X$と分散が$\sigma_{\text{tot}}^2$が次のように得られる。
\begin{equation}
\left\{
\begin{array}{rcl}
X&=&\dfrac{x/\sigma_x^2+y/\sigma_y^2}{1/\sigma_x^2+1/\sigma_y^2}\\
\sigma_{\text{tot}}^2&=&\dfrac{1}{1/\sigma_x^2+1/\sigma_y^2}
\end{array}
\right.
\end{equation}
つまり、誤差の小さいデータ点の重みは大きく、平均値に強く寄与する。
不確かさと精密度と正確度
不確かさとは標準偏差$\sigma$を標本の平均$\bar{x}$で割った値である。例えば、「$10\%$の不確かさ」とは、$\sigma/\bar{x}=0.1$であることを意味する。
精密な(precise)測定とは、分散が小さい値が得られた測定のことを言う。
一方、正確な(accurate)測定とは、真の値に近い値が得られた測定のことを言う。
ポアソン過程
ポアソン分布はある時間間隔で発生する離散的な事象を数えるための分布であり、その式は以下で与えられる。
\begin{equation}
P(n)=\dfrac{\lambda^n\mathrm{e}^{-\lambda}}{n!}
\end{equation}
$\lambda$は期待される、あるいは平均のカウント数である。ポアソン分布の平均と分散は共に$\lambda$である。
$\mathrm{e}^\lambda$のテイラー展開から容易に分かるように、
\begin{equation}
\sum_{n=0}^\infty P(n)=1
\end{equation}
が成り立つ。$N\gg1$のとき(大体$N>20$ならこれを適用して良い。)、$\sigma\simeq\sqrt{N}$である。また、$P(0)=\mathrm{e}^{-\lambda}$である。これはイベントがどのくらいレアかをあらわす。$\lambda\ll1$なら$P(0)\simeq1$なのでイベントは殆ど起こらない。
また、平均$\lambda$のポアソン分布に従う事象が$t=0$で観測されたとき、次の事象が$t=T$までに観測される確率は$P(T)=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda T}$で与えられる。